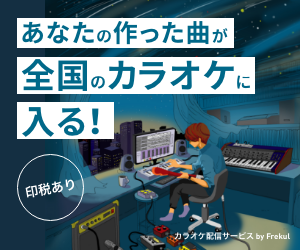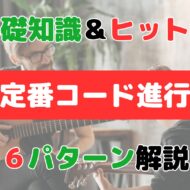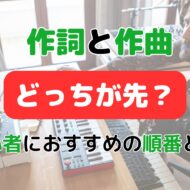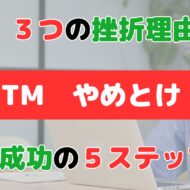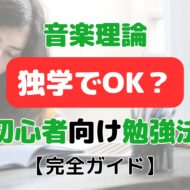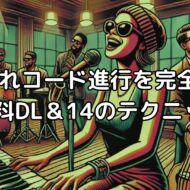ℹ️リンクには広告が含まれる場合があります。
- 作曲と編曲ってどう違うの?
- どっちをどうやって学ぶべき?
音楽制作に関わるなら避けて通れない作曲と編曲。
でも、言葉の意味や役割をはっきりと説明できる人は意外と少ないです。
しかもDTMが普及した今、作曲と編曲の境界はどんどん変化してきています。
必要なスキルや制作の流れも、昔とはすっかり変わってきました。
しっかり理解しておかないと、無駄な遠回りや挫折につながることも。
この記事では、
- 作曲と編曲の違い
- 作業の流れと必要なスキル
- 現代の役割の変化と融合
- 初心者におすすめの学び方
まで、総合的にやさしく解説します。
「作曲と編曲をどうやればいいか分からない」
「これから音楽制作を始めたい」
という方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
【SRM.です!】
音楽のお悩み解決情報発信中!
→無料作曲講座を受け取る🎁
SRM.(エスアールエム)
シンガーソングライター/作曲・音楽活動コンサルタント:音楽活動歴15年以上
詳しいプロフィール
🎁「作曲ができるようになる方法」無料で学べます!
独学でつまずきがちな「作曲のやり方」や「必要なスキル」を、
初心者向けに動画で解説するオンライン講座を公開中。
\今だけ!登録者限定/ 全8回の初心者向け音楽理論講座もプレゼント中!
講座を無料で受け取る作曲と編曲の違い

作曲と編曲の違いは、一言でいえば「メロディを作るか」「メロディを支える音を作るか」です。
- 作曲:
メロディ作り&コード進行 - 編曲:
曲の詳細設定&メロディ以外の伴奏
作曲は、曲のメインとなるメロディを生み出します。
多くの場合、メロディに合うコード進行の基礎もこの段階で決定します。
一方、編曲ではそのメロディとコード進行をもとに、曲全体を彩る音の土台を作っていきます。
ドラムやベース、ギター、ストリングスなどのパートを組み立てるだけでなく、リズムパターンや和音の鳴らし方(ボイシング)まで細かく設計します。
【ボイシングについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください】
・同じコードを違う響きに聴かせられるボイシングの話
例えば、同じコードでもピアノで弾くのか、ギターでかき鳴らすのか、シンセでパッドとして鳴らすのかで印象は大きく変わります
こうした「音のデザイン」を考えるのが編曲の仕事です。
また編曲には、次のような「詳細設定」も含まれます:
- キー:曲の高さ
- テンポ:曲の速さ
- 展開:曲の構成
- 音色:使う楽器
つまり、作曲は「何を歌うか」、編曲は「どう聴かせるか」を決める作業とも言えるでしょう。
「作曲」と「編曲」はよく一緒に語られますが、役割や目的は大きく異なります。
作曲と編曲:音楽制作の流れ

では、作曲と編曲について実際の音楽制作の流れに当てはめながら、それぞれの役割をみていきましょう。
ここでは、ボーカル入りのポップス制作を例に、一般的な流れをみていきます。
下の表は、音楽制作の流れと担当する音楽家を表したものです。
| 内容 | 担当 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 歌詞を作る | 作詞家 | 作曲家が作詞家を兼ねる場合もあり |
| 2 | メロディーを作る | 作曲家 | |
| 3 | コード進行を決める | 作曲家 | |
| 4 | キーを決める | 編曲家 | ボーカリストの音域を考慮 |
| 5 | テンポを決める | 編曲家 | |
| 6 | 展開を考える | 編曲家 | イントロ・間奏・アウトロ・ソロなど |
| 7 | 伴奏に使う音色を決める | 編曲家 | 楽器やエフェクトの設定 |
| 8 | 伴奏を作る | 編曲家 | リズムやフレーズなどを考える |
| 9 | 実際に演奏する | 演奏家 | ボーカルを含む |
| 10 | 演奏を録音する | エンジニア | |
| 11 | ミックス~マスタリング | エンジニア | 音のバランスや規格を整える |
ちなみに、この表では「作詞→作曲→編曲」という順番になっていますが、作詞と作曲の順番は逆になることもよくあります。
【作り方の順番については、こちらの記事をご覧ください】
【初心者向け】作詞作曲どっちが先が正解?順番で変わる曲作りのコツ
まず作詞家が歌詞を作ります。
そして、その歌詞をもとに作曲家がメロディとコード進行を決めます。
次に、そのメロディとコードを受け取った編曲家が詳細設定を考えていきます。
詳細設定を決める際は、以下のようなことを考えて決めていきます。
- キー:
ボーカルが歌いやすいか? - テンポ:
メロディが最も活きる速さは? - 展開:
曲の表現に必要なセクションは?
(イントロ・間奏・アウトロなど) - 音色:
表現に合う楽器やエフェクトは?
詳細設定が決まったら、ドラム・ベース・ギターなど各パートのリズムやフレーズを作り、曲全体に命を吹き込んでいきます。
全ての楽器について、全体の調和をとりつつ展開に沿うようなフレーズを作っていくことになります。
【編曲については、こちらの記事で詳しく説明しています】
・【編曲のコツ!】アレンジのやり方|初心者向け9ステップを実例付きで解説曲作業を公開
作業の分量は編曲の方が多いので、一見すると編曲家の方が負担が大きいように見えます。
しかし、あくまで楽曲の基礎は作曲家が作ったメロディにあります。
作曲が良くないと、いくら編曲を良くてもいい曲になりません。
クオリティーの低いメロディを作ってしまうと、いくら編曲でカバーしようとしても難しいです。
そう考えると、作曲家のメロディ作りも編曲家と同じぐらい重要性が高く大変なものになります。
作曲や編曲は、それぞれが独立した作業というより、音楽制作の中でつながって進んでいきます。
質の高い楽曲は、作曲と編曲の相乗効果によって生まれるものなのです。
DTM時代:作曲・編曲の変化と融合

ここまで見てきたような音楽制作の流れは、現代では大きく変化してきています。
現代はテクノロジーの発達によって、 パソコン1台で音楽制作のほとんどを1人でできるようになりました。
パソコン上での音楽制作を「DTM(デスクトップミュージック)」といいますが、DTMによって作曲と編曲の関係性にも変化が生じてきています。
下の表は、現代の音楽制作の流れと作曲・編曲の関係性を表したものです。
| 内容 | 担当 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歌詞を作る | 作詞家 | 作曲家が作詞家を兼ねる場合もあり | |
| 2 | メロディーを作る | 作曲家 | ||
| 3 | コード進行を決める | 作曲家 | ||
| 4 | デモを作る | キーを決める | 作曲家 | ボーカル音域配慮 |
| テンポを決める | 作曲家 | |||
| 展開を考える | 作曲家 | イントロ・間奏・アウトロ・ソロなど | ||
| 伴奏の音色を決める | 作曲家 | 楽器・エフェクトの設定 | ||
| 伴奏を作る | 作曲家 | リズムやフレーズなどを考える | ||
| 実際に演奏する | 作曲家 | |||
| 演奏を録音する | 作曲家 | 仮歌を含む | ||
| 5 | アレンジを整える | デモの修正 | 編曲家 | |
| 打ち込み修正 | 編曲家 | 実際の演奏の代わりとなる場合が多い | ||
| 6 | 実際に演奏する | 演奏家 | ボーカルを含む | |
| 7 | 演奏を録音する | エンジニア | ||
| 8 | ミックス~マスタリング | エンジニア | 音のバランスや規格を整える | |
たとえば、以前は編曲家が担っていた「音色の決定」や「伴奏の作成」なども、今では作曲家がDTM上で一括して行うケースが一般的になってきました。
さらには、演奏・録音・ミックスといった工程まで一人で担うことも増えています。
DTMでは、作曲家が作ったメロディとコードに加えて、伴奏まで含めた完成形に近いデータ(=デモ)を制作します。
そのうえで編曲家は、プロデユーサーの意向などにより、より楽曲の意図に合った編曲になるように、フレーズの修正や全体の調整を行っていきます。
ここで大幅に編曲が変わり、編曲家が1から編曲を行う場合もありますが、基本的には作曲家が作ったデモをベースに編曲をしていくことになります。
以上のように、作曲家が編曲を兼ねるスタイルが定着してきた背景には、次のようなメリットとデメリットがあります。
- 作曲家のイメージをそのまま形にできる
- 少人数で完結でき、柔軟性が高い
- 制作コストと時間を削減できる
- 作曲家に必要なスキルと負担が大幅増
- メロディ特化の作曲家が活躍しにくい
つまり、現代の音楽制作では「メロディだけ作れる人」ではなく、「メロディから編曲・録音・ミックスまでをトータルでこなせる人材」が求められるようになっています。
こうした変化はプロの現場だけでなく、個人の音楽活動や趣味のレベルでも進んでおり、今やDTMによる「ひとり制作」は主流になっています。
編曲を依頼する:6つのポイント

現代の音楽制作では、作曲家が編曲・演奏・録音までを一人で行うことが増えています。
しかし、必ずしもすべてを自分でこなす必要はありません。
メロディとコードを作るスキルがあれば、その先の工程は信頼できるパートナーに任せるという選択肢もあります。
たとえば「作曲は得意だけど編曲は苦手」「録音やミックスまでは手が回らない」と感じたら、クラウドソーシングを活用して外部に依頼するのも一つの手です。
また、近年では『コライト』という共同制作の形も広まっています。
欧米ではメロディ・編曲・演奏・録音を、それぞれ得意な人が分担するスタイルがよくあります。
日本でも、スキルのマッチングが簡単にできるサービスが増えており、たとえば以下のようなプラットフォームで自分に合ったクリエイターを見つけることができます:
◾️ココナラ:作曲・編曲・ミックスなど、幅広い依頼に対応
◾️クラウドワークス:楽曲制作全般の外注先を探せる
ただし、依頼する際には以下のポイントをチェックしておくと安心です:
- 実績やサンプル音源の質
- 希望ジャンルや雰囲気に対応できるか
- 修正対応の可否と回数
- 参考曲やイメージ共有のしやすさ
- 料金と納期の明確さ
- コミュニケーションの丁寧さやスピード
こうした点を事前に確認することで、トラブルを防ぎつつ、自分のイメージ通りの楽曲を仕上げてもらうことができます。
もちろん、作曲家として編曲や録音スキルを身につけていくことも重要です。
トータルで制作ができる人材は、プロの現場でも重宝されますし、何より自分の表現をそのまま形にしやすくなります。
まずは「自分に必要な部分だけ外注する」という形で、無理なく制作の幅を広げていくのがおすすめです。
作曲編曲に必要なスキルと学び方

作曲と編曲に必要なスキルは実はあまり変わりません。
どちらとも以下のようなスキルが必要になります。
- 音楽理論
- 発想力
- アウトプット力
作曲と編曲では必要なスキルに違いがあるというより、スキルの使い方に違いがあるといえます。
音楽理論
作曲・編曲どちらとも、音楽理論の知識を土台にしないとクオリティ高い曲を完成するのが難しくなります。
メロディにコードをつける、複数の楽器で調和を作る――どちらにも理論的な裏付けがないと上手くいきません。
作曲では、良いメロディを作るための分析力や裏付けとして。
編曲では、複数パートを同時に鳴らすための構造理解として、理論は不可欠です。
知識ゼロの状態では感覚だけに頼ることになるため、とても非効率な作業になってしまいます。
【音楽理論を身につける方法については、以下の記事を参考にしてください】
・【完全ガイド】音楽理論は独学でOK?初心者におすすめの勉強法と失敗しないコツも紹介
発想力
知識だけでは曲を完成することはできません。
発想力とは、以下のような内容をまとめて新たな表現を生み出す力のことです。
- 感受性
- アイデア
- ストック
曲作りは表現することの一つの形なので、曲のテーマや歌詞の内容から情感を感じ取る感受性が必要になります。
また感じとったものをどんな形式で表現するか、というアイデアも思いつかなければなりません。
アイデアが思いつくためには他のアーティストのさまざまな既存曲を聴き込み、その表現方法を自分の頭の中にストックとして記憶しておく必要があります。
【アイデアの発想については、こちらの記事も参考にしてください】
・無意識がアイデアを生み出してくれるようになる。エウレカモーメントの手順をご紹介!
アウトプット力
アウトプット力とは、音楽理論や発想力を使って頭に浮かんだ音楽を実際に音として現実に落とし込むための力です。
以下のようなものが考えられます。
- 作業手順や方法論性
- ツールを使いこなす技術
- 音楽を共有する力
作業手順や方法論とは、作曲や編曲作業を実際にどんな順番でどのように行うかというマニュアルのようなものです。
【手順や方法について悩んでいる方は、こちらの記事を参考にしてください】
・【作曲のやり方】初心者に最適な手順7ステップを解説!
・初心者向け編曲のやり方9ステップを解説【実際の編曲作業を公開】
ツールを使いこなす技術とは、DAWなどのPCによる操作の知識や楽器の演奏技術のことです。
頭に浮かんだ音楽を実際の音として存在させるために必要なスキルです。
【DTMについては、こちらの記事も参考にしてください】
・【DTM作曲やめとけ!?】初心者によくある挫折理由3選と成功する5ステップを解説
音楽を共有する力とは、音楽製作に関わる他のミュージシャンやエンジニアに、自分の創作した音楽やその音楽の創作意図を理解してもらうためのスキルです。
音楽制作の現場では、譜面でのやり取りが基本になります。
自分の作った音楽を譜面に起こす技術や、他の音楽家が作った譜面を読み解く力が必要になってきます。
【アウトプットについては、こちらの記事も参考にしてください】
・【モチベーションを保つには?】インプットとアウトプットをコントロールする話
スキルの使い方の違い
以上説明した3つのスキル、音楽理論・発想力・アウトプット力について、作曲と編曲ではその使い方が異なります。
作曲の場合は3つのスキルを、少ない要素で豊かな表現をするために使っていきます。
作曲のメインであるメロディは、12音とリズムの組み合わせという限られた要素で作り上げなければなりません。
要素が少ないので一見すると素人でもできてしまうように思われます。
しかし要素が少ないということは、説得力あるハイクオリティなものを作るのが難しいことを意味します。
この難しさに取り組むために、3つのスキルが必要になってきます。
編曲の場合は逆に、取り扱う要素が多岐に渡ります。
たくさんの楽器でリズムやフレーズを考えなければなりません。
編曲では多様な要素を統合して調和の取れた音楽を作るために、3つのスキルを使って取り組んでいきます。
おすすめの学び方
作曲や編曲を学ぶには、以下の学び方の中から自分に合う方法で進めてみてください。
1:独学
自分のペースで進めたい人におすすめ。
ブログなど無料コンテンツや書籍、YouTubeなどがおすすめです。
【独学の場合は、こちらの記事を参考にしてください】
・【完全ガイド】音楽理論は独学でOK?初心者におすすめの勉強法と失敗しないコツも紹介
・【作曲本まとめ】初心者にオススメの7冊をご紹介!選び方と読み方も解説
2:スクール
プロから効率的に学びたい方向け。
添削やフィードバックで確実な成長を手に入れられます。
【作曲・編曲・打ち込みなどをまとめて学べるDTM教室がおすすめです】
・DTM歴15年が体験レビュー!初心者におすすめのDTM教室5選〜選び方のポイントとは?
3:オンライン講座
手軽で復習しやすい学習スタイル。自宅で学びたい方にぴったりです。
するめミュージックでは、基礎的な音楽理論が丸っと一通り学べるオンライン講座を無料で配信しています。
もし「何から手をつけたらいいかわからない」という方は、こちらの講座から始めてみてください。
まとめ
作曲と編曲の違いや、それぞれの役割やスキル、現代的な制作スタイルについて見てきました。
| 内容 | 担当 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 歌詞を作る | 作詞家 | 作曲家が作詞家を兼ねる場合もあり |
| 2 | メロディーを作る | 作曲家 | |
| 3 | コード進行を決める | 作曲家 | |
| 4 | キーを決める | 編曲家 | ボーカリストの音域を考慮 |
| 5 | テンポを決める | 編曲家 | |
| 6 | 展開を考える | 編曲家 | イントロ・間奏・アウトロ・ソロなど |
| 7 | 伴奏に使う音色を決める | 編曲家 | 楽器やエフェクトの設定 |
| 8 | 伴奏を作る | 編曲家 | リズムやフレーズなどを考える |
| 9 | 実際に演奏する | 演奏家 | ボーカルを含む |
| 10 | 演奏を録音する | エンジニア | |
| 11 | ミックス~マスタリング | エンジニア | 音のバランスや規格を整える |
特にDTMが普及した今、作曲と編曲の境界は柔軟になり、自分の得意を活かしながら音楽制作に関わる道が広がっています。
| 内容 | 担当 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歌詞を作る | 作詞家 | 作曲家が作詞家を兼ねる場合もあり | |
| 2 | メロディーを作る | 作曲家 | ||
| 3 | コード進行を決める | 作曲家 | ||
| 4 | デモを作る | キーを決める | 作曲家 | ボーカル音域配慮 |
| テンポを決める | 作曲家 | |||
| 展開を考える | 作曲家 | イントロ・間奏・アウトロ・ソロなど | ||
| 伴奏の音色を決める | 作曲家 | 楽器・エフェクトの設定 | ||
| 伴奏を作る | 作曲家 | リズムやフレーズなどを考える | ||
| 実際に演奏する | 作曲家 | |||
| 演奏を録音する | 作曲家 | 仮歌を含む | ||
| 5 | アレンジを整える | デモの修正 | 編曲家 | |
| 打ち込み修正 | 編曲家 | 実際の演奏の代わりとなる場合が多い | ||
| 6 | 実際に演奏する | 演奏家 | ボーカルを含む | |
| 7 | 演奏を録音する | エンジニア | ||
| 8 | ミックス~マスタリング | エンジニア | 音のバランスや規格を整える | |
初心者のうちは、「まず何を学べばいいの?」「どんな手順で曲を作ればいいの?」と迷いがちです。
そんなときは、体系的に基礎から学べる教材や講座を活用するのが近道です。
するめミュージックでは、初心者の方でもゼロから作曲・編曲の基本を学べる無料のオンライン講座をご用意しています。
「なんとなく感覚でやっている」「理論を学びたいけど本は難しい」と感じている方にぴったりの内容です。
また作曲や編曲に関する知識については、以下の記事でも詳しく説明しているので参考にしてください。
【オススメ記事】
・【作曲のやり方】初心者に最適な手順7ステップを解説!
・【作曲に使える】コード進行を考えるための基礎知識と定番進行6パターンをヒット曲とともにご紹介
・初心者向け編曲のやり方9ステップを解説【実際の編曲作業を公開】
・独学で音楽理論を学ぶために知っておくべき5つのこと~オススメの学習方法を紹介
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
「作曲したいけど、、、
なかなか形にならない…」
そんなあなたに向けて、
無料で「作曲の全体像」がわかる講座を用意しました。
- ✔ 作曲の4つのスキル+1つの考え方
- ✔ ステップ動画で順番に理解できる
- ✔ 今だけ基礎音楽理論講座つき

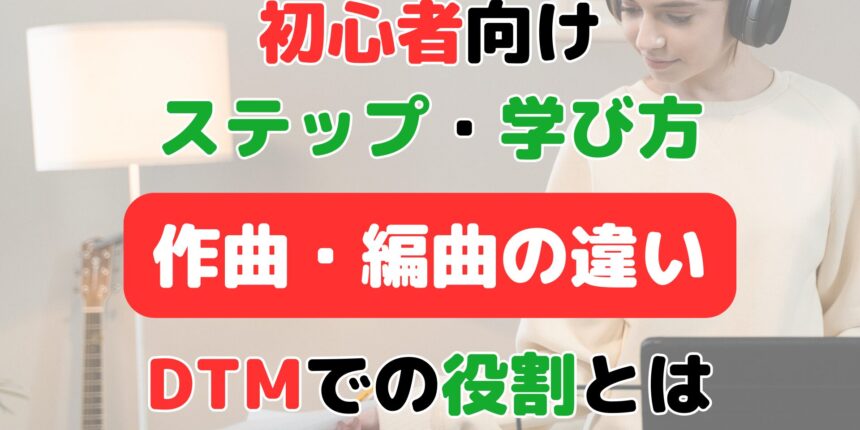


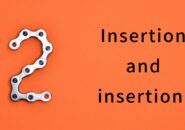








.jpg)