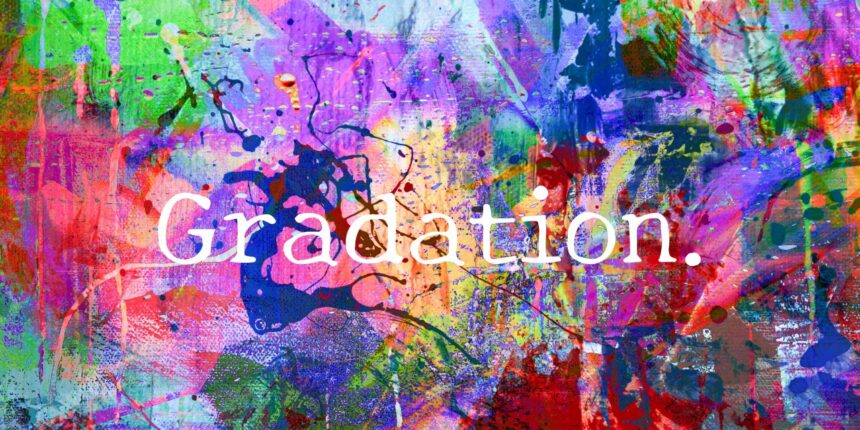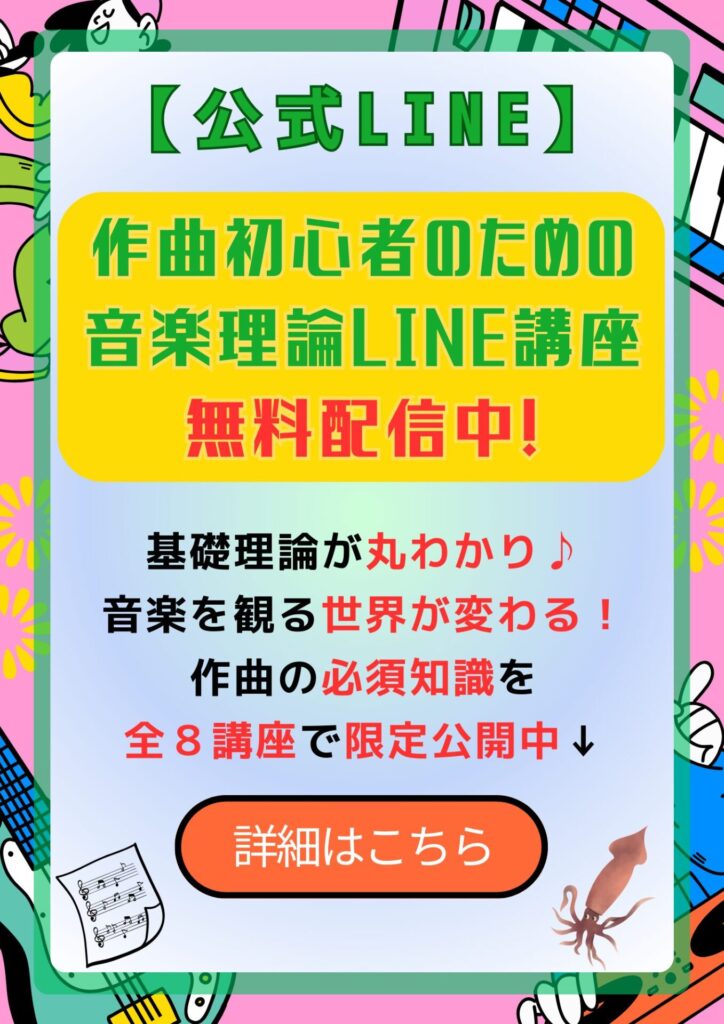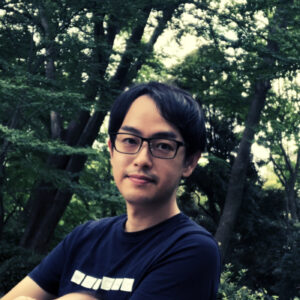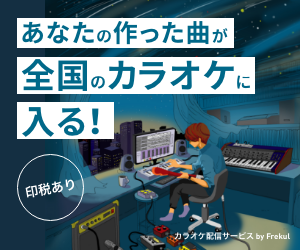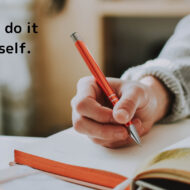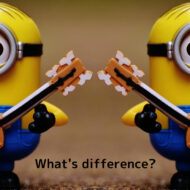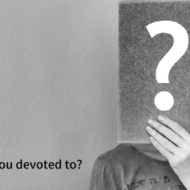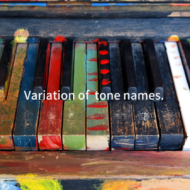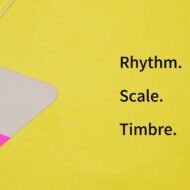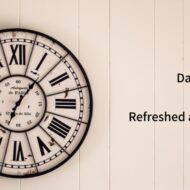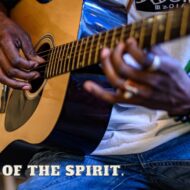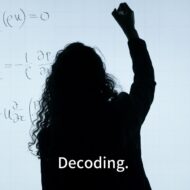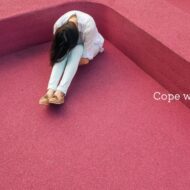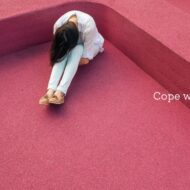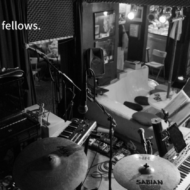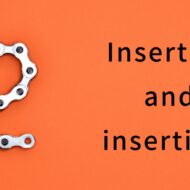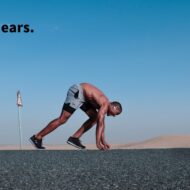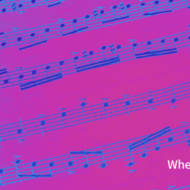楽曲のことを語るとき、「この曲はメジャーキーだよね」とか「マイナーの曲は暗いイメージの曲だよね」とかいったりします。
この、メジャーとマイナーってそもそも何なんでしょうか。
ダイアトニックコード
Popsなど普段良く耳にする音楽は大抵、ダイアトニックコードという7つのコードを中心につくられています。
詳しくはこの記事で書いていますが、
有名なドレミファソラシド〜の音階を元にしてできる7つのコードがダイアトニックコードで、具体的にはこのコードたち。
(ドを始まりとして考えた場合)
①ド・ミ・ソ・シ:CM7
②レ・ファ・ラ・ド:Dm7
③ミ・ソ・シ・レ:Em7
④ファ・ラ・ド・ミ:FM7
⑤ソ・シ・レ・ファ:G7
⑥ラ・ド・ミ・ソ:Am7
⑦シ・レ・ファ・ラ:Bm7(♭5)
それぞれの頭の音を繋げるとドレミファソラシド〜になっています。
始まりは何の音でも構わないので、例えばレを始まりに指定した場合は、全て1全音づつズレることになります。
メジャーとは
これらのコードを使って曲をつくるとき、①のコード(上の例ではCM7のコード)を中心に曲をつくると、その曲はメジャーの曲(またはメジャーキーの曲)と呼ばれます。
中心につくる、とはどういうことでしょうか。
それは、①のコードが鳴ったときに「落ち着いた、安定した」と感じられるコード進行を組むということです。
感覚的すぎてよくわからない!と思うかもしれませんが、主に二つのポイントを意識すると上手くいくと思います。
ドミナントコードを意識する
ドミナントコードとは、①のコードに対して4度下のコード。つまり⑤のコードになります。
①がCM7なら⑤はG7です。
①のコードの直前に⑤のコードを置くようにすると、①のコードの「落ち着いた、安定した」という感覚が強調されます。
例えば、サビのドアタマに①のコードを置いて、その直前(Bメロなどの最後)に⑤のコードを置く、というのがよくある方法です。
①のコードの位置を意識する
①のコードを使うときは、小節やフレーズの1番最初に使うようにしましょう。
1番最初に出てくると、このコードがこの曲の中心なんだな、という感じが出ます。
ただし、必ずしもフレーズの最初に使わなければならないわけではないので、それは表現したい内容との兼ね合いになります。
その場合、曲の終わりに鳴る最後のコードに①のコードを使うようにするなど、①のコードが中心であるということを示す工夫をしましょう。
マイナーとは
マイナーとは、ダイアトニックコードの⑥のコード(上の例ではAm7のコード)を中心につくった曲のことです。
⑥のコードが「落ち着いた、安定した」と感じられるようにコード進行を組むということです。
この場合も、上で書いた2つのポイントを意識することは同じです。
⑥のコードの場合、ドミナントコードは③のコード(上の例の場合はEm7)になるので注意して下さい。
またマイナーの場合、この③のコードはドミナントセブンスコードに変化させて使われることがよくあります。
上の例でいくと、Em7をE7にして使うということです。
これはドミナントセブンスコードが、中心のコードを強調する効果があるためです。
聴き比べると「解決した!」という感じが強いのがよくわかるので、実際に弾いて聴いてみて下さい。
使うコードは同じ
メジャーとマイナーは、中心のコードが変わっただけで、使うコードの種類は同じです。
(③のドミナントセブンスコードは例外)
これで2つの世界観を使い分けられるなんて、何か不思議ですよね。
ダイアトニックコードの力強さを感じます。
明るい?暗い?
よく「メジャーは明るい雰囲気で、マイナーは暗い雰囲気」なんて言われます。
実際にそのように使いわけることも可能です。
しかし、個人的には単純に二極化して捉えるのはもったいないかな〜、と考えています。
メジャーでも切ない陰鬱さとか、マイナーでもテンションの上がる感じとか、いろんな曲をつくることは可能です。
明るい・暗いの2つでなく、混ぜ具合によってカラーが段々と変化していく、グラデーションのような関係と捉えるのがいいのかな、と思います。
といったわけで今回は、メジャーとマイナーについて基本的な考え方を書いてみました。
グラデーションの考え方を用いれば、メジャーとマイナーを混ぜながら、表現したい内容をより精密に表現できると思います。
以上参考になれば嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。